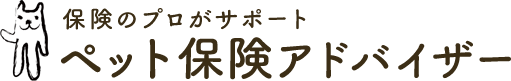バベシア症を発症した犬の治療費はいくら?症状や予防方法も解説!
2023年9月1日

バベシア症はマダニを媒介して感染します。発症した犬の治療費は高額になりがちで、輸血が必要になってくるとさらに高くなります。完治は難しく再発リスクも高いため、バベシア症に感染しないための予防が重要です。
この記事では
・犬のバベシア症の治療方法や治療費
・犬のバベシア症の予防方法
「バベシア症」とは
バベシア症とは
- ケンカ
- 輸血
犬のバベシア症は治る?うつる病気なのか
犬のバベシア症は
とされています。
現時点では、完全にバベシア原虫を犬の体内から駆除する方法が見つかっていないためです。
また、他の動物にうつる病気でもあります。
血液に寄生するため
ことで感染します。
そのため
- 闘犬
- 犬同士の咬傷(ケンカ)
が主な感染経路です。
まれに感染に気付かず、汚染血液を輸血することで感染するケースもあります。
犬のバベシア症とは?原因や症状、検査方法を解説!
バベシア症とは主に
そもそもバベシア症とは?血液検査等の検査方法も解説!
バベシア症は
・バベシア・カニス(Babesia canis)
・バベシア・ギブソニ(B. gibsoni)
バベシアは血液検査で見つけることが可能です。
貧血がみられたら主に血液検査を行いますが、貧血と血小板減少が高確率で見られるとバベシア症が疑われます。
「血液塗抹」という検査方法でバベシアの有無を調べ、追加のPCR検査で最終診断を下します。
犬のバベシア症の原因は?マダニを介して感染する!
犬のバベシア症の原因は
- フタトゲチマダニ
- ヤマトマダニ
- クリイロコイタマダニ
- ツリガネチマダニ
で、全国的にはフタトゲチマダニとヤマトマダニが分布しています。
暖かい地方である西日本を中心にバベシア症の発生が多く報告されていますが、全国どこででもマダニと接触する可能性はあるので注意が必要です。
犬のバベシア症の症状は?貧血や発熱等の症状を解説!
犬のバベシア症の主な症状は貧血があげられます。貧血にも種類があり、バベシア症は「溶血性貧血」と呼ばれるものです。
・発熱
・可視粘膜の蒼白
・元気消失
・食欲不振
・疲れやすい
・尿が濃くなる
溶血性貧血とは赤血球が何らかの原因で破壊されて貧血に陥る状態です。赤血球には寿命がありますが、寿命よりも先に破壊されます。
犬の貧血は重症度が高く命に関係するため、貧血の症状がみられたら動物病院で治療を受けましょう。
また、診察を受けてわかる症状は
- 血小板減少
- 脾腫
などがあります。
症状自体は気づきにくいものも多いので普段の状態を知っておき、見逃さないよう注意が必要です。
犬のバベシア症の治療法や治療費用、予防法を詳しく紹介!
犬のバベシア症は主な症状が貧血です。貧血の症状に合わせた治療を行います。
バベシア症は原虫を体内から駆除するのは難しく、完治困難な病気です。再発のリスクも高いので、治療費を知っておき準備を整えておきましょう。
かからないよう予防をしておくことも重要です。
犬のバベシア症の抗生剤の投与等の治療法、治療費を紹介!
犬のバベシア症の主な治療方法は
・抗マラリア薬
・抗生物質
の投与です。ただしどれも緩和的な効果にとどまり、特効薬とまではいきません。
バベシア原虫を体内から完全に駆除するのは難しく、治療によって症状が落ち着いても体内に原虫が存在する状態となります。
治療費
バベシア症の治療費は、動物病院によって違いがあるものの
- 診察料
- 検査費用(血液検査・尿検査・レントゲン検査・超音波検査)
- 薬の処方
貧血がひどい場合には輸血をするケースもあり、
犬のバベシア症の予防法は?マダニ駆除剤等が有効!
犬がバベシア症は命に関わるケースもあり、再発のリスクも高い恐ろしい病気です。そのためかからないための予防が重要となってきます。
・草むらに近づけない
・ダニ駆虫薬の投与
犬の体にマダニを見つけたら?
散歩後にはマダニなどがくっついていないか確認して、家に持ち込まないようにしましょう。
もし犬の体にマダニが付着していたら、獣医師に専用器具で取り除いてもらってください。
専用器具を使わず指で引っ張ると
そのため除去は動物病院で行いましょう。
バベシア症にかかりやすい犬種や年齢、性別はある?
バベシア症にかかりやすい特定の犬種や性別はありません。全犬種にかかるリスクがあります。
一方年齢に関しては
といわれています。
その理由は外を走り回る体力があるため、知らないうちにマダニが付着してしまう可能性が高いからです。
また猟犬など山に入ることが多い犬や、地域によってはかかるリスクが変わってきます。
定期的な予防やダニ駆除剤を持ち歩くなどの対策をしておきましょう。
もしもの時に備えてペット保険に加入しておくのがおすすめ!
ペット保険とはペットの治療費を負担してくれるものです。
加入内容によっては
もあります。
バベシア症を含めた犬の治療費は100%自己負担です。治療費の負担を考えると満足に治療を受けさせてあげられないケースもあります。
バベシア症は再発のリスクが高く、場合によっては何度も治療が必要なこともあり高額になりがちです。
高額な治療費のうち50%でも補償してもらえたら助かりますよね。もしもの時のペット保険は非常に役に立ちおすすめです。
月々の保険料もコースによっては1,000円未満のものもあるため、家計の負担になりません。
バベシア症だけでなくケガや病気の治療費を考えて、ペット保険を検討してみても良いでしょう。
よくある質問
バベシア症の治療後、症状がなくなりました。治ったといえますか?
バベシア症の治療後は原虫が体内に存在する「キャリア」の状態で、症状がなくなったことから「寛解(かんかい)」と呼ばれます。
寛解は「完治」とは違い、キャリアであるため再発しないよう注意しなければいけません。
少しでも異常を感じたら獣医師に診てもらいましょう。
犬の体にマダニが付着していました。バベシア症に感染しますか?
指でマダニをつまんでしまうと感染リスクが上がってしまいます。決して自分で取ろうとしないでください。
貧血の重症度によりますが、80~90%の犬はバベシア症にかかっても約2ヵ月で快方に向かいます。恐ろしい病気ではあるものの、慌てずに治療を行うことが重要です。
ペット保険は必要?

ペットには公的な保険制度がありません。そのため治療費の自己負担額は100%です。
もしもの時に、お金を気にせずペットの治療に専念できるよう健康なうちにペット保険に加入することをおすすめします。
また、病気になった後では加入を断られる可能性があります。
ペット保険比較表や記事を活用するのがおすすめ!
ペット保険比較アドバイザーでは、ペットに合った保険の選び方やペットの健康に関するお役立ち記事を公開しております。
記事と合わせて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。
また、保険会社のデメリット等も理解できるので、後悔しないペット保険選びができます。
ペット保険への加入を検討されている方はぜひご活用ください。
【バベシア症の犬の治療費は?症状や予防方法も解説】まとめ
今回、ペット保険比較アドバイザーでは
・犬のバベシア症の治療方法や治療費
・犬のバベシア症の予防方法