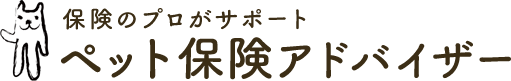犬のご近所さんトラブルはどう回避する?散歩中やドッグランでは?
2024年5月27日

・犬のトラブルに巻き込まれたらなすべきこと
・トラブルを回避するために飼い主さんのできること
家の中で起こりやすい犬のトラブルと予防方法
犬を飼っていると、大なり小なりトラブルはつきものです。
よくあるトラブル
最もよくあるトラブルが、ご近所さんからの苦情ではないでしょうか。
苦情に対処するには先手必勝!
ふだんから挨拶はもちろん、良好な関係を築いておきましょう。
「何かご迷惑をおかけしていませんか?」と、顔を合わせたときに声かけをするのがおすすめです。
【ご近所さんからの苦情の例】
・鳴き声がうるさい!
・飛びついてきた!
・噛まれた!
・犬の毛が飛んでくる!
・変なにおいがする(糞尿や犬の臭い)!
苦情を言うか言わないかは別にして、犬を飼ったことがない方でもいくつかは被害者側として経験があるかもしれません。
とくに多いのが「鳴いてうるさい!」というものです。
最近は「ペット可」の賃貸物件も増えてきており、アパートなどでも犬を飼う人が増えてきています。
飼い主さんにとっては「それほどでもない」と思っていても、隣室やご近所さんの中には夜間勤務をして昼休んでいる人、ナーバスになっている受験生、リモートワークをしている人など、鳴き声に対して不快な思いをしている人がいるかもしれません。
また、「配送業者の人が来たときに急に飛び出してきて飛びついたと」という例も見られます。
予防方法
犬があまりにも吠えると、時には家族でも「静かにしなさい!」と怒りたくなる時もあります。
しかし、それは人間の言い分で犬には吠える理由があります。
【犬が吠える理由】
・警戒
・威嚇
・要求
・興奮
・ストレス など
まず、犬が吠える原因を飼い主さんが察知して、それに対応したしつけが必要です。
「飼い主が留守の間に吠えてうるさい」というのも比較的多いケースです。
例えば、家の外が見えている場合、車やバイク、鳥などを見つけて吠えることがあります。
留守中に室外が見える方が気分転換になるのでは?と思われるかもしれませんが、刺激が強すぎる場合があります。
対処法としては、刺激がないようにカーテンや家具などで目隠しをして外が見えないように工夫しましょう。
それでも吠るようなら、別の原因を探る必要があります。
チャイムの音に反応して吠えたり、外から来た人に対して攻撃的な場合は、クレートトレーニングをしておきましょう。
その場面になったら「ハウス」とコマンドを出し、ハウスの中が安全なことを教えておきます。
また、室内を汚さないように室外でブラッシングするのもマナー違反です。
抜けた毛が風に舞ってご近所さんの所へ飛んでいきます。
排泄物に対する配慮も必要です。
ペットシートや犬の排泄物などはゴミ収集の日まで2~3日間家に置いておくことになりますが、臭いが漏れないように工夫しましょう。
べランダなど外に置いている場合、風に乗ってに隣家に臭いが届いてしまいます。
周囲の人みんなが犬好きとは限りません。「このくらいのこと」という言い訳はできません。ちょっとした臭いや、毛が飛んでいくのも不快に思われるかもしれないので注意しましょう。
犬の鳴き声がうるさくて迷惑だと、隣人とトラブルが生じて傷害事件に発展した例や、自宅の庭にいた犬が脱走して人に襲い掛かったなどというニュースを見聞します。噛まれた人が死亡したという例もあります。
脱走した犬が人を襲うと、飼い主は「管理不十分」で刑事罰を適用され、犯罪として扱われる場合があります。
このような惨事にならないようにトラブルの芽は早めにつみとりましょう。
散歩中に起こりやすい犬のトラブルと回避方法
犬にとって楽しいはずの散歩タイムですが、そこでもトラブルが待ち受けています。
犬にとっても室外は危険がいっぱいです。
よくあるトラブル
・人や犬に急にとびかかる
・他の犬に咬みつく
・交通事故
散歩中、すれ違っただけなのに「吠えられた」「吠えた」というトラブルが最も多いのではないでしょうか。
ただ、それだけならごく普通のことかもしれませんが、興奮して飛び掛かっていくようなら問題です。
また、曲がり角の出会いがしらにいきなり吠えて歩行者が驚いて転倒という例もあります。
うっかりリードが離れたり首輪がすっぽ抜けると、トラブルの被害者または加害者になる危険性があります。
予防方法
散歩に連れて出る場合、リーダーウォークの訓練をして、犬に「飼い主さんの側にいれば安全」ということを教えましょう。
- リーダーウォークとは
- リードを使用して飼い主と犬の距離を付かず離れずの距離(リードが張らない距離)に保って歩くことを言います。犬は飼い主さんの左側につき、飼い主さんより前に出ないように歩きます。
とはいえ、訓練ができていなくても散歩には出かけることが多々あると思います。
散歩中に人や犬に対して吠えるのは恐怖、好奇心や興奮、メンタルの弱さ、自分のテリトリーに入ってくるな、というメッセージです。
きちんとしつけができるまでは、相性の悪い犬の姿が見えたら回り道などして道を変えるのが無難でしょう。
犬の散歩はリードを着けて短めに持ち、犬から目を離さず、周囲の歩行者や犬に気を配りながら行いましょう。
【トラブルを避けるために散歩中に注意すること】
・歩きスマホは厳禁
・伸びるリードは使わない
・黙って他人の犬に近づけない
・引っ張らせない
・排泄物の処理はきちんとする
公園などを散歩コースにしている飼い主さんもおられると思いますが、リードを外しての散歩はルール違反です。
ドッグランで起こりやすい犬のトラブルと回避方法
犬が楽しめるはずのドッグラン。
ここでもトラブルが起きる可能性があります。
よくあるトラブル
・興奮した犬に衝突される
・排泄
・吠える
ドッグランに愛犬と子どもを連れて来ている飼い主さんもよく見かけます。
小さなお子さんは常に保護者の方の側にいるようにしましょう。
犬に追いかけ回される、ぶつかって転倒、いきなり触ったとき犬が驚いて噛みつくなどのトラブルが生じることがあります。
犬の全力疾走は小型犬であってもかなりの威力があるので衝突すると危険です。
また、トラブルになった場合、大きな犬の方が優勢になるのは当然なので、多くのドッグランでは犬の大きさ別にエリアを区切っています。
また、ドッグランのトライアル用にパーソナルスペースを用意している所もあります。
予防方法
ドッグランに入ったら、すぐにリードを外さないでしばらくつけたままにしておくとよいでしょう。
とっさのときに、リードを踏むことですぐに静止できます。
また、リードをはずしてからも犬から目を離さないように気を付けましょう。
ドッグラン利用に際しては最低限のしつけはしてから出かけるのがマナーです。
マテ・オスワリ・コイなどのコマンドに従え、呼び戻しができるようにしつけておきましょう。
その他
・排尿をしたら⇒水を流す
・吠え癖がある場合⇒口輪(かわいいデザインのものもあります)
トラブルの原因のほとんどがしつけができていない、社会化不足です。
また、物の取り合いでトラブルになることもあるので、おもちゃや食べ物の持ち込みを禁止です。
犬同士がけんかになった時、ドッグランではリードを着けていないことがほとんどで、引っ張って止めることはできません。
【犬同士のけんかの止め方】
・犬の目をタオルなどで覆う(視界を遮る)
・鼻を叩く
・水をかける
・大きな音を出す(金属音など)
犬がトラブルを起こさないために飼い主さんのできること
犬を家族に迎えた場合、他の人や物に害を加えないように努めなくてはなりません。
動物愛護管理法では動物の所有者または占有者に対して「動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」と規定しています(7条1項)。
【犬がトラブルをおこさないためにすべきこと】
・社会化
・しつけ
・リーダーウォーク
【社会化】
犬は、生まれてから最低でも8週間は母犬や兄弟たちと暮らし、犬社会のコミュニケーションやルールを教わります。
そして生後3~12週ころを「社会化期」と呼び、さまざまな刺激に慣れやすい時期です。
この間に経験したことは、将来的にも受け入れやすいと言われています。
いろいろな人や犬、車やバイクの音、外の景色など、少しずついろんな体験をさせましょう。
もちろん抱っこのままで大丈夫です。この経験が少ないと、人や物に吠えやすくなるかもしれません。
【しつけ】
生後3ヶ月を過ぎるころになると警戒心や自我が育ち始めて問題行動が増えていきます。
適切なタイミングを見極めてしつけを始めましょう。
吠えに対するしつけ、待て・来い・お座りなどのコマンドに従えるようにしつけをします。
しつけの方法については、ドッグトレーナーさんたちが動画をあげていますのでそちらが参考になると思います。
【リーダーウォーク】
しつけの一環となりますが、外に出るときは犬の身を守るためにも大切なことです。
リードを引っ張らないで、飼い主さんの歩調に合わせて同じように歩くことが犬の身を守ることにつながります。
犬がどんどん引っ張って歩くとリードが離れて他の人に飛びついたり、交通事故も心配です。
犬がトラブルを起こした・巻き込まれたときの対処法
うちの子は絶対大丈夫、と思っている飼い主さんもいますが、動物にとって「絶対」はありません。
万一の時に対処法を知っておきましょう。
愛犬が被害を受けた場合
飼い主さんにとって子供同然のペットであっても動物は法律上では「物」として扱われます。
噛まれてけがを負った場合、治療費は相手側に払ってもらえるのでしょうか。また、その根拠はどこにあるのでしょうか。
犬は飼い主さんの所有物であり、噛まれてケガをすれば、治療費が損害というとらえ方になります。
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」との民法の規定があり、治療費は噛んだ犬の飼い主に賠償請求できます。
まずは治療が優先です。すぐに動物病院を受診しましょう。
愛犬がトラブルを起こした場合
他の犬を噛んでしまったときの対処方法は被害を受けたときと同様です。
動物病院を受診してもらい、連絡先(電話番号やメールアドレスなど)も忘れずに聞いておきます。
あわせて保健所への届出も行っておきましょう。
【人を噛んだ場合】
まず相手に誠心誠意お詫びをしましょう。
対処方法は、犬を噛んだ場合より厳格になり、保健所への連絡が義務づけられています。
・ワクチン証明書を提示
・翌日までに地域の保健所に連絡する
・2日以内に病院を受診してもらう
犬のトラブルはペット保険の補償対象です
犬が他のペットや人に危害を及ぼした場合、ペット賠償責任特約(オプション)を付帯していれば費用が補償されます。
【補償されないケース】
・飼い主の同居家族にけがをさせた
・ドッグランでの犬同士のトラブル
・犬を他人に預けているときの事故
ペット賠償責任特約はペット保険にオプションとして付帯できるものですが、付帯できるかどうかは保険会社によって異なります。
ペット保険以外にも、クレジットカード・自動車保険・火災保険などに「賠償責任特約」が付帯している場合もあるので確認しておきましょう。
よくある質問
近所の犬が朝早くや夜遅くなどに吠えて迷惑しています。どこへ相談したらよいのでしょうか。
犬の吠えている声があまりにもひどくて迷惑ならば、相談窓口は次のようになります。
保健所(保健所より、飼い主に注意が行く)、マンションなどの場合は管理事務所に言って注意してもらう、警察に通報(警察から通報があった旨飼い主に伝える)などの方法があります。
犬は放し飼いにしても問題ありませんか。
ペット保険は必要?

ペットには公的医療保険制度がありません。そのため診療費の自己負担額は100%です。
もしものときに、お金を気にせずペットの治療に専念できるよう健康なうちにペット保険に加入することをおすすめします。
また、病気になった後では加入を断られる可能性があります。
ペット保険比較表や記事を活用するのがおすすめ!
ペット保険比較アドバイザーでは、ペットに合った保険の選び方やペットの健康に関するお役立ち記事を公開しております。
記事と合わせて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。
また、保険会社のデメリット等も理解できるので、後悔しないペット保険選びができます。
ペット保険への加入を検討されている方はぜひご活用ください。
【犬のご近所さんトラブルはどう回避する?散歩中やドッグランでは?】まとめ
今回、ペット保険比較アドバイザーでは
・犬のトラブルに巻き込まれたらなすべきこと
・トラブルを回避するために飼い主さんのできること