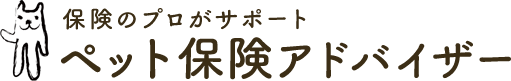猫の子宮蓄膿症の手術費用は?かかりやすい猫種や年齢も解説!
2023年11月8日
アビシニアン, アメリカン・ショートヘア, アメリカンカール, エキゾチックショートヘア, サイベリアン, ソマリ, ノルウェージャン・フォレストキャット, ブリティッシュ・ショートヘア, マンチカン, ミックス(雑種), ミヌエット, ラグドール, ロシアンブルー, 子宮蓄膿症

この記事では
・猫の子宮蓄膿症の予防法
・猫の子宮蓄膿症におすすめのペット保険
猫の子宮蓄膿症とは?手術にもリスクや後遺症のある危険な病気!
猫の子宮蓄膿症とはメス猫がかかる病気で
です。
猫の子宮蓄膿症は犬よりも発症率が低い傾向にあります。
その理由は黄体ホルモンの分泌期間の違いにあります。
- 黄体ホルモンとは
- 犬や猫に発情期が来ると妊娠を助けるために分泌されるホルモンのこと。
黄体ホルモンは妊娠を助けると同時に、子宮と膣を繋げる「子宮頸部」を開きやすくしてしまうことから細菌が入り込みやすくなります。
その結果子宮蓄膿症にかかる可能性が上がってしまいます。
猫は犬よりも黄体ホルモンを分泌する期間が短いため、猫の方が子宮蓄膿症の発症率が低いと言われています。
なぜ黄体ホルモンの分泌の期間に差があるのでしょうか。
それは犬と猫の妊娠形態の違いにあります。
・猫は交尾をした際の刺激によって排卵を起こす「交尾排卵動物」
自然排卵型は定期的に排卵が行われます。
一方、交尾排卵型は交尾が行われないと排卵も起こりません。
交尾排卵型は排卵が起こらないと黄体ができても弱く、子宮蓄膿症にかかるほどの脅威になることが少ないのです。
このことから黄体ホルモンの分泌期間に差があり、それによって猫が子宮蓄膿症にかかりにくいことが分かります。
手術のリスクや後遺症
それでももし猫が子宮蓄膿症にかかってしまったら、一般的な治療として子宮と卵巣を摘出する手術を行います。
手術ということから麻酔のリスクがあります。
持病持ちや高齢の場合だとすぐに手術が出来ないケースもあるので注意が必要です。
また、術後の後遺症としては子宮と卵巣を摘出するため出産が出来なくなることです。
愛猫の子供を残したいと考えている飼い主さんにとっては残念ですが、愛猫の命には代えられません。
一方で愛猫の出産を考えていない飼い主さんは避妊手術を受けておくことをおすすめします。
猫の子宮蓄膿症とは?原因や症状について解説!
犬ほど発症率が高くない猫の子宮蓄膿症ですが、猫でもかかることはあるので原因や症状を知っておくことは重要です。
ここからは猫の子宮蓄膿症を詳しく解説していきます。
そもそも猫の子宮蓄膿症とは?放置すると手遅れになるのか
猫の子宮蓄膿症とは「子宮に膿が溜まる病気」です。
子宮内で膿が溜まるまでの過程は
②子宮内に細菌が侵入
③細菌が増殖、子宮内は膿が溜まる
です。
最初は子宮内に細菌が侵入し、子宮内膜炎を発症します。
- 子宮内膜炎とは
- 子宮が何らかの原因で炎症を起こしてしまった状態のこと。
実は子宮蓄膿症は子宮内膜炎が進行した状態です。
中には子宮蓄膿症まで行かない子もいますが、子宮内膜炎を発症したにも関わらず正しい治療を受けられなかった猫の多くは子宮蓄膿症を患ってしまいます。
発情が終わると子宮頸部は閉じて細菌の逃げ場がなくなり、子宮内膜炎の症状が進行してしまうからです。
子宮蓄膿症は子宮内膜炎の進行した姿であることから、症状が見られる時点でかなり悪化しているケースが多くあります。
子宮蓄膿症自体進行も速く、放置すると手遅れになる危険性が高くなります。
いつもとおかしいと感じたらすぐにでも動物病院で受診してください。
猫の子宮蓄膿症の原因は?発情期や妊娠した猫は要注意!
子宮蓄膿症の原因は
であることを先述しました。
若い年齢で発情期中のメス猫は、オスを受け入れやすくするために子宮頸部が緩んでいます。
そのため細菌も入りやすくなってしまうのです。
原因になる細菌は大腸菌、ブドウ球菌、サルモネラなどです。
このことから発情期中の猫には子宮蓄膿症に注意が必要なことが分かります。
しかし子宮蓄膿症は細菌感染に加えて他の原因があります。
体力や免疫力の低下
実は子宮蓄膿症は子宮内に細菌が侵入したら必ず発症するわけではありません。
健康な猫であれば子宮内に細菌が侵入しても白血球がやっつけてくれます。
しかし体力や免疫力が低下していると細菌をやっつけることが出来ずに子宮内で細菌が増殖、子宮内膜症から子宮蓄膿症に進行します。
発情期中のメス猫はオスの精子を受け入れやすくするために通常よりも免疫力が低下しています。
加えてこの発情期というのは猫にとってストレスも疲労も大きいものです。
発情期中は活動的になり消費エネルギーも増え疲労も蓄積する反面、食事量も睡眠時間も減少します。
さらに妊娠中や出産後でも免疫力の低下で子宮蓄膿症にかかるリスクは上がります。
発情期中、妊娠、出産後は猫の子宮蓄膿症には気を付けなければいけません。
猫の子宮蓄膿症の症状は?
子宮蓄膿症の主な症状としては
・お腹が膨らむ
・元気がなくなる
・食欲不振
・嘔吐
などがあげられます。
子宮蓄膿症には子宮頸部が開いているか閉じているかで大きく2種類に分けられます。
子宮頸部が開いている「開放型」
子宮頸部が開いた状態で子宮蓄膿症まで進行してしまったのがこの状態です。
子宮頸部が開いていることから
特徴があります。
そのため猫が陰部を舐める行動が増えます。
多くの飼い主さんは陰部からの膿と舐めるといった行動で子宮蓄膿症に気づきます。
ただし膿の量が少ないと、猫が舐めてしまうなどして発見が遅れることもあるので注意が必要です。
子宮頸部が閉じている「閉鎖型」
子宮内に細菌が侵入したまま発情が終わり、子宮頸部が閉じてしまうと細菌の逃げ場がなくなります。
その後子宮内膜症にかかってしまうと、進行して「閉鎖型」の子宮蓄膿症となってしまいます。
子宮頸部は閉じてしまっているため、子宮内に溜まった膿も出ることができません。
そのため
のが特徴です。
気付かずに放置すると体外に排出されない膿は溜まり続け、いずれ子宮壁に穴が開いたり避けたりします。
子宮壁からあふれ出した膿はお腹の中でも細菌感染を続け腹膜炎になります。
こうなると早急な手術と治療を行わないと100%助かりません。
治療を行ったとしてもすでに手遅れで助からないケースも多くあります。
そのため愛猫の少しの変化に気づくことが、子宮蓄膿症の早期発見にはとても重要です。
猫の子宮蓄膿症の検査法や治療法、治療費と予防法を解説!
猫の子宮蓄膿症の検査方法はおもに
・レントゲン
・エコー(超音波検査)
です。
血液検査では白血球の数値が上がることにより子宮蓄膿症が疑われます。また急性腎不全を発症している場合にも血液検査の数値に現れます。
もし急性腎不全を発症していれば麻酔をかけることはとても危険です。
そのため手術の必要があるケースでは先に腎臓の状態を安定させてからになります。
血液検査に加えてレントゲンやエコーで子宮の膿を確認出来たら「子宮蓄膿症」と診断が下され、これらのデータや画像診断をもとに治療方針を決めていきます。
猫の子宮蓄膿症の治療法は?抗生物質等の薬や手術を解説!
子宮蓄膿症の治療法は
が一般的です。
手術内容としては子宮と卵巣の摘出なので避妊手術と同じです。
ただし子宮蓄膿症では細菌感染している状態での手術となるのでリスクはかなり高くなります。
手術中は細菌感染の二次被害を防ぐため、子宮に傷をつけないよう慎重に摘出しなければいけません。
術中に抗生物質での腹腔内の洗浄も行い、術後も抗生物質を投与されます。
摘出術中や術後にも全身に細菌が感染していないか、状態が悪化していないかなどの経過観察が必要となるので単純な手術ではないことを覚えておく必要があります。
手術をしない方法も
また手術をしない治療方法もあります。
・繁殖させたいなどの強い要望があった場合
などでは内科療法が取られ、その方法として抗生物質が使用されます。
内科療法では子宮頸部を開く働きをする薬剤を注射して子宮内に溜まった膿を排出し、抗生剤や抗菌薬を用います。
有効な抗生物質を確実に投与するため、膿の中の細菌を培養して原因菌を特定したり、抗生物質の感受性検査を行う場合もあります。
この方法は子宮が残っていることから再発の可能性が高く、治療後のケアも必要となるため基本的には外科手術が適応となります。
子宮を温存することは子宮蓄膿症再発のリスクだけでなく、乳腺腫瘍にかかる可能性も残ります。
外科手術が出来ないケースでなければ子宮摘出手術を受けた方が二つのリスクを回避することができます。
猫の子宮蓄膿症の治療費は?入院費用や手術費用も実例で紹介!
手術を行うことで完治と再発のリスクがなくなる子宮蓄膿症ですが治療費が気になるところです。
平均的な内容別の治療費は下記のようになります。
| 内容 | 費用 |
| 検査(血液検査、エコー、レントゲンなど) | 50,000円程度 |
| 手術 | 45,000~50,000円程度 |
| 入院 | 5000円程度/日 |
子宮蓄膿の多くは約1週間の入院が必要なので総額約150,000円の治療費がかかると考えていいでしょう。
これらの費用は動物病院によって違いがありますが、子宮蓄膿症で手術をしたある猫さんの実例は
・子宮摘出手術(麻酔など手術に関わる費用含む) 99,500円
・入院費(皮下注射など含む) 5,500円/日
でした。
上記の猫さんは5日間の入院で総額142,150円の治療費がかかっています。
もし急性腎不全などで全身の状態が悪かったり、子宮が破裂している場合などでは入院や治療が長引きます。
そのようなケースだと上記以上に治療費がかかることが考えられます。
また、治療方法の中に内科治療があることを先述しました。
内科療法だと子宮内の膿を取り除くための治療が、子宮頸部を開く薬剤と抗生物質で行われます。
完治するためには時間もかかるため総合的にみると治療費も上がり、結果的には手術した時の料金と変わらない額になります。
そのため費用の負担を減らしたいという理由で内科治療を行うことはおすすめできません。
猫の子宮蓄膿症の予防法は?避妊手術がおすすめ!
子宮蓄膿症はかかってしまうと命を脅かす恐ろしい病気です。そのため予防法が重要になってきます。
子宮蓄膿症の一番の予防法は
です。
避妊手術には子宮蓄膿症を予防できるといったメリットの他にも
・望まない妊娠、出産を防ぐことができる
・発情がなくなりストレスが緩和される
などがあげられます。
さらに避妊手術は比較的若いころに行うことが多いため、手術や麻酔に対するリスクも少なくて済みます。
ちなみに避妊手術には2種類あり
・卵巣のみ摘出
のどちらにするかは獣医師と相談のうえで飼い主さんが選択することができます。
この2つの違いは、卵巣のみ摘出だと傷口が小さくて済むことから猫への負担が減ることです。
子宮を残すことで、子宮蓄膿症やその他子宮に関する病気にかかる可能性の有無は意見が分かれています。
飼い主さんの意見が尊重されますが、子宮の病気防止目的であれば子宮と卵巣両方摘出してもいいのではないでしょうか。
子宮蓄膿症にかかりやすい猫種や年齢、猫の状態は?
子宮蓄膿症の恐ろしさが分かってくると自宅の愛猫がかかりやすい猫種なのか、気を付けるべき年齢なのか気になります。
実は子宮蓄膿症は
です。
猫種で発症率が変わってくるわけではありません。
また年齢も関係なく、猫が妊娠できる体になると発症するリスクがあります。そのため早くて1歳で子宮蓄膿症にかかることもあります。
発症の確率が上がるとすれば5歳以降でしょう。猫の5歳はヒトで言う36歳くらいです。
その辺りから加齢に伴い抵抗力などの衰えが考えられます。
タイミング的には子宮蓄膿症は猫が発情期を迎えていたり妊娠しているとかかりやすくなるので、この状態の猫は気をつけてあげるようにしましょう。
猫の子宮蓄膿症におすすめの保険は?
猫の子宮蓄膿症の治療費はペット保険でも基本的には補償されますが、中には補償の対象外としているペット保険もあります。
また上述したとおり猫の子宮蓄膿症は約1週間の入院が必要なので総額約150,000円の治療費がかかります。
内訳には検査費用等も大きな割合を占めるので、しっかり補償してほしいと考えるのであれば、「通院・手術・入院を補償するフルカバー型」のペット保険がおすすめです。
子宮蓄膿症とは別で、猫は腎不全等の慢性疾患にかかりやすいです。
ペット保険は基本的に1年の保険期間の契約となり、自動的に更新していく形になります。つまり、毎年契約の更新の審査をされることになります。
腎不全のような完治が難しい病気は、次年度の契約から補償の対象外となってしまう可能性も高いです。
ペット保険比較アドバイザーでは、猫及び猫の子宮蓄膿症におすすめのペット保険をご紹介します。
おすすめの理由としては、
・更新時に条件を付けないペット保険の中でも、手術に強い
の2点があります。
猫の子宮蓄膿症の治療を考えると、一番おすすめはアニコムです。
アニコムでは保険金請求回数に応じた保険料割増制度ありますが、「腸内フローラ測定」を年一で行えるため、猫の死因ランキング1位である腎不全の予防までできる他、外出しずらい猫には有効な健康チェックです。
測定結果によっては血液検査も無料で受けることができます。
ただし、細かい補償内容や金額についてはもちろん違いがありますので必ず重要事項説明書や保険約款、パンフレットや公式HPを確認してください。
あくまで参考ですが、そもそも病気にさせたくないと考える飼い主様にはアニコムがおすすめです。
| メリット | デメリット | |
| ・歯科治療も補償 ・「腸内フローラ測定」等の予防型サービスも付帯 ・通院は一日当たり14,000円×年20日まで補償(補償割合70%プラン) |
保険料が高い 保険金請求回数に応じた保険料割増制度あり |

2年目以降のご契約継続について
弊社の商品の保険期間は1年間ですが、ご契約には「継続契約特約」を適用して引受をさせていただいておりますので、解約等のお申し出がない限り満期後は、原則ご契約は自動的に継続となり、終身ご継続いただけます。
※ご注意
・ご契約者または弊社より別段の意思表示があった場合には、ご契約は継続となりません。
・自動的にご契約が継続とならない場合や、商品改定により保険料、補償内容などが変更となる場合があります。
引用:重要事項説明書
補足:先天性疾患が発症する前に!遅くとも7.8歳までには加入しよう
ペット保険は、加入する前に発症している先天性疾患や既に発症している病気や疾患は補償の対象外となります。
そのため、病気になってから保険に加入しようとしても、肝心のその病気の治療費は補償の対象外になってしまいます。
また、加入後に発見できた病気であっても先天性疾患を補償の対象外としているペット保険や、慢性疾患にかかると更新できない保険もあります。
また一般的にペット保険では8~12歳で新規加入年齢を設定していることがほとんどです。早いところでは7歳で新規加入を締め切るペット保険もあります。
「健康なうちに加入しないと意味がない」「また年齢制限に引っかからないから保険の選択肢が広がる」という意味で遅くとも7~8歳までにはペット保険の加入、少なくとも検討をすることをおすすめします。
補足ですが、アニコムやプリズムコールではシニア向けのペット保険商品もあります。しかし保険料も高くなり、補償内容のグレードも普通のプランより下がってしまいます。
高齢・シニア向けのペット保険については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしてください。
よくある質問
猫の子宮蓄膿症の手術費用はペット保険の対象ですか?
子宮蓄膿症は手術での子宮摘出治療が一般的なため、治療費が高額になります。
いざという時に満足な治療を受けさせるためにも、ペット保険に加入しておくことが重要です。
犬の陰部から膿が大量に出ています。これは子宮蓄膿症の手遅れな状態なのでしょうか。
むしろ「開放型」の症状に近く、膿が排出されていると考えられます。
とは言え子宮蓄膿症は急激に症状が悪化してしまう恐ろしい病気です。
一刻も早く動物病院で治療を行ってください。
ペット保険は必要?

ペットには公的な保険制度がありません。そのため治療費の自己負担額は100%です。
もしもの時に、お金を気にせずペットの治療に専念できるよう健康なうちにペット保険に加入することをおすすめします。
また、病気になった後では加入を断られる可能性があります。
ペット保険比較表や記事を活用するのがおすすめ!
ペット保険比較アドバイザーでは、ペットに合った保険の選び方やペットの健康に関するお役立ち記事を公開しております。
記事と合わせて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。
また、保険会社のデメリット等も理解できるので、後悔しないペット保険選びができます。
ペット保険への加入を検討されている方はぜひご活用ください。
【猫の子宮蓄膿症の手術費用は?かかりやすい猫種や年齢も解説!】まとめ
今回、ペット保険比較アドバイザーでは
・猫の子宮蓄膿症の予防法
・猫の子宮蓄膿症におすすめのペット保険