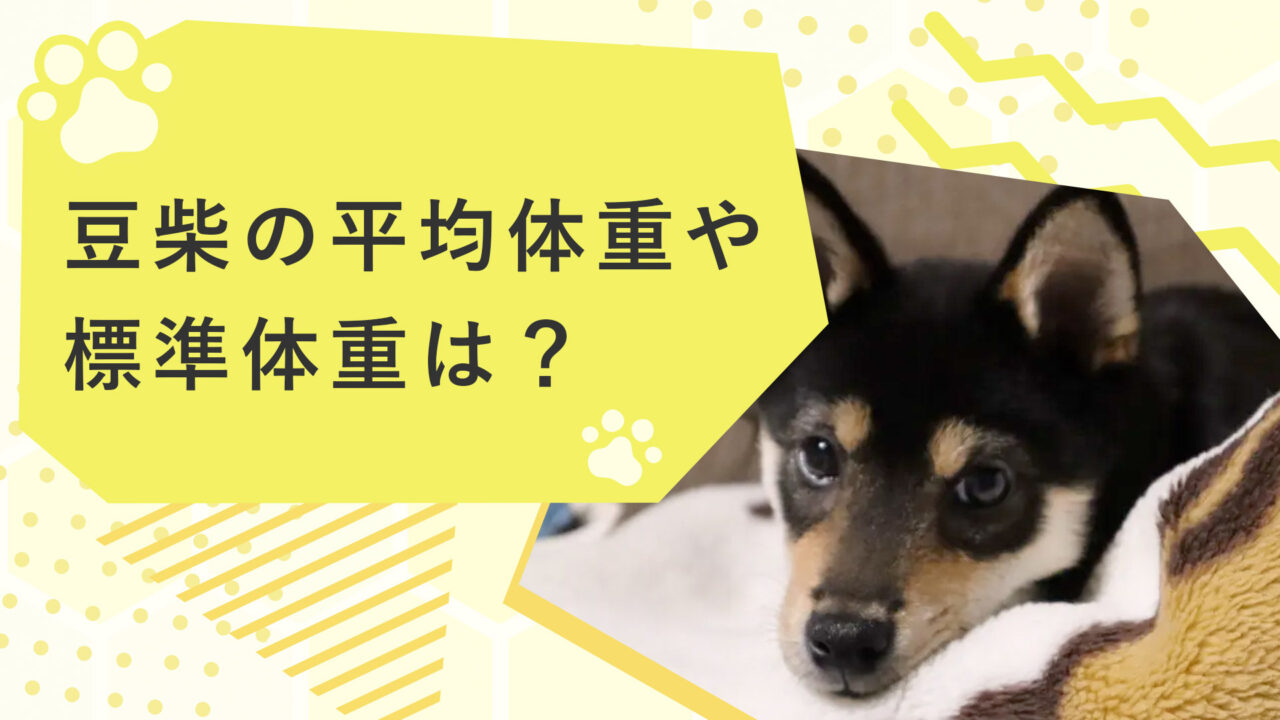猫が片目をつぶる時はストレスを訴えているときもありますが、結膜炎等の病気の可能性もあります。また目を閉じる等の愛情表現の可能性もあるので些細な変化に気づいてあげましょう。
・猫が片目をつぶる3つの要因
・猫に多い目の病気と基本的な治療法
・猫の目を守るためのストレス対策
猫が片目をつぶる意味とは?
猫がこちらを見てウインクしたり目を細める行為には意味があります。
一般的に猫がウインクをこちらに向けてくるのは呼びかけに対する返事や親愛のサインとされていますが、目の状態によっては目の病気のサインかもしれません。
この記事ではウインクにおける親愛と病気の分かれ目ポイントを具体的に解説します。
猫が片目をつぶるのは何が原因?ストレスや愛情表現等の原因を解説
猫が片目をつぶる原因は様々ですが、今回は3つのケースに分けて解説します。
猫が片目をつぶる原因①愛情表現やアイコンタクト
猫の愛情表現は犬と同じように、目や尻尾で伝えてくることが多いです。
しかし、犬に比べて体全体を使ったボディランゲージや、喜怒哀楽を表情で伝えてくれることが少ないため、猫の愛情表現はわかりにくいことが多いです。
猫が行う目を使った愛情表現には
・飼い主と目があった後、目を閉じるまたは細める
などがあります。
尻尾を使った愛情表現には
・声をかけたときに尻尾の先を少し揺らす
などがあります。
またアイコンタクトや尻尾以外の愛情表現では
・体を寄せてくつろぐ
・飼い主の体の一部を舐める
・ゴロゴロと喉を鳴らす
など、何気ない行動の中に猫の愛情は隠れています。
猫が片目をつぶる原因②ストレス
猫の目は愛情だけでなく、猫自身のストレスも私達に伝えてくれます。
猫は繊細で周囲の環境の変化を嫌う動物なので、少しの変化でも飼い主が思っている以上にストレスを感じることがあります。
猫のまばたきは1分間に3〜5回程度とされていて、人間と比べるとかなり少ないです。
そのため、頻繁に目をパチパチさせたり、片目をつぶるような仕草が増えたときは、なにか生活の中で変化したことがないかチェックしてみてください。
猫が片目をつぶる原因③病気
猫が片目をつぶる原因として、ストレス以上に注意しなければいけないのが病気です。
猫の目の病気には目にゴミが入るなどして起こる比較的軽い症状のものから、眼球自体に傷がついてしまったり、まぶたの一部が外に飛び出してくるなどの重い症状のものまであります。
猫に起こりやすい目の病気は次の章で詳しく解説します。
猫が片目をつぶる原因として考えられる病気を解説!
愛猫の目の動きに違和感を感じた時、病気であればいち早く気がついてあげたいものです。
そんなときのために、今回は猫に多い目の病気を4つ解説します。
こんな場合は要注意!病気を疑うべきまばたき・ウインクとは?
親愛のサインとしてのウインクと病気によるまばたきには違いがあります。
愛情表現と病気の違いは主に以下のようになっています。
親愛と病気のまばたきの違い
・常に目がしょぼしょぼしている
・涙で常に目の周りが濡れている
・目が充血している
・目やにの量が多い
・目の周りが赤い
・目の周りが腫れている
・目を痛そうにしてしきりに気にしている
といった症状や行動があるようなら病気の可能性が高いです。
逆に言えばこれらの症状がなく、元気や食欲などにも問題がなければ、ただ片目をつぶっているだけで病気の可能性は低いでしょう。
また、眠いときや寝起きのときに目が半開きのまましばらく過ごしている子もいます。
しかし、これらはあくまでも1つの基準に過ぎないので、気になるようであれば一度動物病院を受診されることをおすすめします。
考えられる病気①:結膜炎
結膜炎とは目の結膜(まぶたの裏にある粘膜や白目)に炎症が起きている状態です。
結膜炎の原因は様々ですが、代表的なのは以下のとおりです。
・異物の侵入(砂や埃など)
・アレルギー
・免疫介在性疾患
・他の目の病気からの続発
などがあります。
結膜炎の場合は、ウイルスや細菌感染によるものが多いため、体力が十分でない子猫に見られることが多いです。
また目やにが増えることが多いため、大量に出た目やにを拭き取らずにそのままにしておくと目やにが糊のようになり、目が開きにくい状態になったり、目やにがカチカチに固まり目が開かない状態になることがあります。
治療は主に点眼薬を使用します。
しかし、症状の状態や原因によっては内服薬も同時に処方されることも多いです。
そして目やにが出ていたら拭き取るなど、目の周りを清潔に保つことも大切です。他の病気から発症している場合は原因となっている病気の治療もあわせて行われます。
治療期間は感染症が原因の場合は2〜3週間ほどで回復します。
しかし、症状が重度だったり基礎疾患などがある場合は更に長期間の治療が必要になる場合があります。
考えられる病気②:角膜炎
角膜炎とは目の角膜(目の表面を覆っている膜)が炎症を起こしている状態です。
角膜炎の原因は主に
・アレルギー
・感染症
・他の目の疾患による合併症
などがあります。
中でも角膜炎の原因として最も多いのが外傷です。
そのため、お外に遊びに行く子や多頭飼育のお家の場合などは猫同士のケンカにより目を怪我してしまうことが少なくありません。
外傷による角膜炎の治療は結膜炎と同様に目薬による治療がメインになります。
また、角膜の損傷の度合いによっては角膜の保護のためにエリザベスカラーや動物用のコンタクトレンズを一定期間装着することもあります。
治療期間は角膜の傷の深さによって変わってきますが、小さく浅い傷であれば通常は3〜7日ほど、そうでない場合では1〜2週間ほどで治る事が多いです。
他の病気から発症している角膜炎の場合は、原因となっている病気の治療も同時に進めていく必要がありますので、治療期間は個体差が大きくなります。
考えられる病気③:眼瞼炎
眼瞼炎(がんけんえん)は眼瞼(まぶた)の周りに炎症が起きている状態です。
まぶたには上まぶたと下まぶたがあり、片方だけ炎症が起きることもあれば、両方に起こることもあります。
そのため目の周りが赤く腫れたり、目の周りの毛が抜けたりすることがあるので外見の変化から気が付きやすいです。
眼瞼炎の原因は様々ですがよく見られるのは以下のとおりです。
・まぶたの異常(先天的、後天的)
・他の目の疾患からの続発
・病原体による感染(細菌、ウイルス、寄生虫)
などがあります。
眼瞼炎の治療も結膜炎や角膜炎の治療と同じです。
目薬や眼軟膏などをメインとした点眼治療を行い、痒みなどが強い場合はエリザベスカラーなどを使って、目をこすらないようにしていきます。
眼瞼炎の原因が他の疾患や感染症から来ている場合は、先に原因となっている基礎疾患や感染症の治療を優先させます。
眼瞼炎の治療期間は適切な治療を行えば2〜3週間程度です。
考えられる病気④:眼瞼内反症・眼瞼外反症
眼瞼内反症(がんけんないはんしょう)と眼瞼外反症(がんけんがいはんしょう)は共にまぶたがめくれてしまっている状態です。
眼瞼内反症はまぶたが内側にめくれるため、まぶたがきちんと閉じない状態になります。
また、まぶたやまつ毛が直接眼球に触れることで以下の症状が見られることが多いです。
・強い痛み
・まぶたの痙攣
などがあります。
眼瞼内反症の原因は様々ですが主に
・怪我が治った後のまぶたの変形
などが挙げられます。
眼瞼外反症はまぶたが外側にめくれるため、まぶたがピッタリと閉じにくい状態になります。
そしてまぶたで守られているはずの眼球がむき出しになることで以下の症状が現れます。
・ドライアイ(乾燥)
・流涙症(涙が増える)
などがあります。
眼瞼外反症の主な元として考えられるのは
・後天的な顔のたるみ(加齢や甲状腺機能低下症、顔面神経の麻痺)
・手術のミス
などです。
眼瞼内反・外反症の治療も主に点眼薬や眼軟膏を使ったものになります。
しかし、目薬などで症状がおさまらない場合は、まぶたを正常な形に整える整形手術を行うこともあります。
また、重度の眼瞼内反・外反症の場合でも、猫が子猫の場合では体の成長が落ち着くまで目薬などの対処療法で眼球を保護し、成猫になった時点で手術を行う場合もあります。
猫のストレスとは?原因や片目つぶる以外の症状、解消法を解説!
猫のストレスの原因は?多頭飼いや室内飼い等の原因を解説!
人が置かれている環境によってストレスの原因が変わるように、猫もどのような環境下で生活しているかによってストレスの原因が変わってきます。
例えば、室内飼育であっても単頭飼育か多頭飼育かではストレスの受け方は違ってきます。
多頭飼育の場合、猫同士で各自のテリトリー(縄張り)を持つ傾向があります。
その猫にとってのお気に入りの場所や特定の家具やクッションなどがテリトリーになります。
テリトリーは人間に例えるとシェアハウスの個人部屋のようなものです。
食事場所やトイレは共用でも、個人の部屋へ勝手に入るのは共同生活を営んでいく上でのタブーです。
そのため勝手に他人(同居猫)に入ってこられるとストレスを感じるのです。
ですので多頭飼育の場合は特に、その猫にとってのテリトリーを確保する必要があります。
多頭飼育されている猫たちは、同じ家を共有する仲間でもありますが同時にライバルでもあります。
お互いのルールが破られた時、相手に対して不快感を抱くのは人も猫も同じです。
猫のストレス行動は?片目つぶる、嘔吐やイライラ等の症状を解説
猫がストレスを感じたときに現れる症状は様々ですが、その中の1つとして片目をつぶるというものがあります。
片目をつぶる症状は他の猫とのケンカなどによる外的要因が多いですが、病気の可能性もあるのでおかしいと感じたらすぐに動物病院へ相談してください。
また猫によってはストレスを感じると食後に吐き戻してしまう子もいます。
ストレスからくる嘔吐であれば暮らしの工夫の次第で改善が期待できます。
しかし嘔吐は食道や内臓の異常などでも起こります。
そのためおかしいと感じたら一度動物病院で検査を受けて下さい。
猫のストレス発散法を解説!構いすぎない、運動させることが大切
人それぞれ性格があるように、猫にもぞれぞれ性格があります。
そのためあまり人にかまってほしくないクールなタイプの子もいれば、たくさんかまってほしい甘えん坊タイプの子もいます。
しかしどんな性格の子でも構いすぎるのは猫にとってよくありません。
クールタイプの子は言わずもがなですが、甘えん坊タイプの子ではたくさんかまってもらえるのが日常になってしまうと、飼い主が何らかの理由で長期的に不在になると強いストレスを感じることが多いです。
また室内飼育の猫は運動不足になりやすい傾向にあります。
猫にとって運動不足はストレスの原因になりますので、飼い主が積極的におもちゃなどを使って遊んであげることが運動不足やイライラ解消に繋がります。
猫におすすめのペット保険は?
ここでは猫に合ったおすすめのペット保険、比較・選び方について解説します。
全てのペット保険で補償の対象外である去勢の費用等の項目は除き、あくまで保険会社・プランで差別化になるポイントに絞って解説します。
他サイトのようなランキング形式ではなく、あくまで猫目線で解説していきます。
猫のペット保険加入の選び方のポイント
・歯科治療(歯周病等)
③通院・手術・入院を補償するフルカバー型のペット保険の中でも通院は他社と比較しても手厚いか
④更新の際に「来年度からの傷病や部位補償の対象外」とする可能性がないか
①猫のなりやすい病気が補償されるか確認
ペット保険は保険会社によって補償する病気や、補償の対象外となる項目が異なります。
中には猫がなりやすい、歯周病を含む一切の歯科治療を補償の対象外としているペット保険も存在します。例えば「プリズムコール」では一切の歯科治療が補償の対象外です。
また、「日本ペット少額短期保険:いぬとねこの保険」では「歯肉に触れる治療は補償されるが、歯に触れる治療は補償の対象外」といった細かい制限があります。
特に歯科治療は保険会社によって補償されるかが異なりますので、必ず保険約款や重要事項説明書を確認することをおすすめします。
また公式HPでも「保険金のお支払いできない事例」の中に記載されていることがほとんどですので必ず確認しましょう。
補足になりますが、予防目的の歯石除去等は全てのペット保険で補償の対象外なので注意しましょう。
猫がなりやすい病気で補償の対象外か確認すべき病気
②加入後に発症した先天性、遺伝性疾患が補償されるか
全てのペット保険で加入前に発症している先天性、遺伝性疾患は基本的には補償の対象外となってしまいますが、加入後に発症した先天性、遺伝性疾患を補償するかどうかは保険会社によって異なります。
猫種によっては、なりやすい遺伝性疾患があります。例えばスコティッシュフォールドでは 骨軟骨異形成症という遺伝性疾患が存在します。
こちらも併せて公式HP内の「保険金をお支払いできない事例」や保険約款・重要事項説明書を確認し、加入後に発症した先天性疾患が補償されるかしっかり確認しましょう。

③通院・手術・入院を補償するフルカバー型のペット保険の中でも通院補償の手厚さを重視するのがおすすめ
猫がなりやすい病気である「腎臓病」や「膀胱炎」は長期もしくは複数回の治療が必要になる疾患です。また「尿結石」は症状が重い場合、外科手術を伴う高額治療が必要になる傷病です。
そのため、猫には「通院・手術・入院を補償するフルカバー型のペット保険」に加入することがおすすめです。
しかし、猫は腎臓病等の慢性疾患になりやすいのに対し、そこまで手術の可能性は高くありません。そのため猫にはフルカバー型の中でも通院補償が他社より手厚いペット保険に加入することをおすすめします。
【通院治療費】
・年間平均診療費 : 272,598円
・平均診療単価 : 9,329円
・年間平均通院回数 : 15.2回
参考:アニコム損保「家庭どうぶつ白書2019」
参考:猫との暮らしとお金「猫が慢性腎臓病になったときにかかる費用はどれくらい?」
(あくまでも統計による平均なので一つの参考資料として見てください)
④更新の際に「来年度からの傷病や部位補償の対象外」とする可能性がないか
ほとんどのペット保険が一年契約となっており、契約を毎年更新していくことで終身の補償となっています。
つまり、ペット保険に加入すると毎年契約更新の審査があります。
中には「前年度にかかった傷病や慢性疾患」等の、特に治る見込みが少ない、再発の可能性が高い慢性疾患を、更新の際に「来年度から補償の対象外とします。」と条件を付け加えてくる保険会社があります。
もちろん中には「更新の際に条件を付け加えることはありません」といった記載をしているペット保険もあります。
猫がなりやすい「腎臓病」は慢性疾患のためかかってしまったら一生の付き合いが必要な病気です。
加入を検討しているペット保険会社の「更新時の対応」についても必ず確認することをおすすめします。
また、ペット保険比較アドバイザーではそういった情報も一つの記事内でまとめていますのでぜひ一度ご確認ください。
猫におすすめのペット保険をご紹介!
最後に、今回ペット保険比較アドバイザーでは猫におすすめのペット保険をご紹介します。
おすすめの理由としては上記で説明した猫のペット保険の選び方、ポイントや条件をすべて満たしているからです。
アニコムでは保険金請求回数に応じた保険料割増制度ありますが、「腸内フローラ測定」を年一で行えるため、猫の死因ランキング1位である腎不全の予防までできる他、外出しずらい猫には有効な健康チェックです。
測定結果によっては血液検査も無料で受けることができます。
ただし、細かい補償内容や金額についてはもちろん違いがありますので必ず重要事項説明書や保険約款、パンフレットや公式HPを確認してください。
あくまで参考ですが、そもそも病気にさせたくないと考える飼い主様にはアニコムがおすすめです。
| メリット | デメリット | |
| ・歯科治療も補償 ・「腸内フローラ測定」等の予防型サービスも付帯 ・通院は一日当たり14,000円×年20日まで補償(補償割合70%プラン) |
保険料が高い 保険金請求回数に応じた保険料割増制度あり |
アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」

アニコム損保では、ご家庭の予算やライフスタイルに合わせて最適な保険プランが選べます。「どうぶつ健保ふぁみりぃ」は通院・入院・手術をフルカバーしてくれるプランです。「どうぶつ健保ぷち」は入院と手術をカバーしてくれるプランで、ふぁみりぃの約1/3の保険料で加入することができます。「どうぶつ健保しにあ」は8歳以上から加入ができ、加入年齢の上限が無く、入院・手術の診療費を補償するプランとなっています。
ペット保険の加入は早めに!7~8歳までの加入がおすすめ
ほとんどのペット保険は、加入前に発症している病気(既往症)や先天性疾患は補償対象外です。
そのため、病気になってから加入を検討しても手遅れになる可能性があります。
また、ペット保険によっては
- 加入後に発覚した先天性疾患も補償の対象外
- 慢性疾患になると更新ができない
なんてケースも。
さらに、新規加入の年齢制限もあり、7~10歳で多くのペット保険が受付を締め切ります。
ペット保険の選択肢を広げるためにも、健康なうちに遅くとも7~8歳までに加入を検討しましょう。
なお、8歳を既に過ぎていても高齢ペットに向けたペット保険があります。
詳しくは別記事で解説しているので、ぜひチェックしてみてくださいね。
よくある質問
- 愛猫の目が開けづらそう…。何日様子を見てもいい?
-
猫が目を開けにくそうにしていても、涙や目やに、まぶたの腫れなどが見られない場合は1日様子を見てもいいでしょう。
しかし、徐々に充血してきたり、涙や目やに、まぶたの腫れや痛みなどがあるようなら様子見はせず、すぐに動物病院へ行くようにして下さい。 - 猫の目が閉じたままになる病気があるって本当?
-
猫の目の病気や状態によっては、治療の為や今後の生活の質の向上を目的として眼球を摘出することがあり、結果として目が閉じたままになる場合があります。猫の目の病気は放置しておくと重症化してしまうと失明してしまうものや、再発を繰り返してしまうものもあるので注意が必要です。
ペット保険は必要?

ペットには公的医療保険制度がありません。
そのため診療費の自己負担額は100%です。
もしものときにお金を気にせずペットの治療に専念できるよう、ペット保険に加入することをおすすめします。
また、病気になった後では加入を断られる可能性があります。
ペットが元気なうちに加入を検討しましょう。
無料で活用!ペット保険比較表や、豆知識コラム、LINE無料相談がおすすめ
大切なペットのために、まずはLINEで気軽に相談してみませんか?
ペット保険アドバイザーでは、あなたのペットにぴったりの保険選びをサポートします。
ペットの健康に関するお役立ち記事や、詳しい比較表もご用意していますので、ご家族に合った後悔しない保険選びにご活用ください!
まとめ
今回、ペット保険比較アドバイザーでは
・猫のアイコンタクトは飼い主に向けた愛情表現の1つであること
・感染症や怪我からくる猫の目の病気は早期治療を行えば完治するものが多いので、早めの治療が重要だということ
・運動におけるストレス解消は猫同士のケンカ削減や肥満防止に繋がりメリットが大きこと
について解説してきました。
人語を話すことができない猫にとってアイコンタクトは重要なコミュニケーションツールです。
愛猫の目を守り、より良いコミニュケーションのためにも眼の異変を感じたら放置せずすぐに動物病院で相談をするようにして下さい。
ペット保険比較アドバイザーでは、ペット保険に関する記事も掲載しております。
併せて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。
ぜひご活用ください!