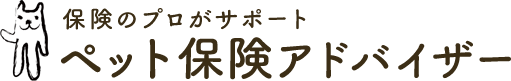猫の甲状腺機能亢進症の治療費は?余命や末期症状についても解説!
2023年11月8日
アビシニアン, アメリカン・ショートヘア, アメリカンカール, エキゾチックショートヘア, サイベリアン, スコティッシュフォールド, ソマリ, ノルウェージャン・フォレストキャット, ブリティッシュ・ショートヘア, ペルシャ猫, マンチカン, ミックス(雑種), ミヌエット, メインクーン, ラグドール, ロシアンブルー, 甲状腺機能亢進症

この記事では
・猫の甲状腺機能亢進症の原因
・猫の甲状腺機能亢進症の治療法
・猫が甲状腺機能亢進症になった場合の余命
猫の甲状腺機能亢進症とは
甲状腺機能亢進症は、甲状腺に良性の腫瘍が発生することで甲状腺ホルモンの分泌が活発になる内分泌疾患です。高齢の猫がかかりやすいとされています。
甲状腺ホルモンは全身の代謝をよくする働きをしていますが、異常に分泌されると代謝が上がりすぎてさまざまな臓器に負担がかかります。
逆に甲状腺ホルモンの分泌が以上に減少する(甲状腺機能低下症)と、代謝が悪くなり臓器機能が低下し皮膚や被毛にも変化が出ます。
猫の甲状腺機能亢進症の余命や寿命について
猫が甲状腺機能亢進症になった場合の末期症状や寿命について紹介します。
甲状腺機能亢進症の末期症状
猫の甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが異常に分泌され代謝がよくなることで、年齢のわりに食欲が旺盛になったり攻撃的になったりします。
甲状腺機能亢進症は自然治癒する病気ではないため、治療しないで放置していると体力がどんどん落ちていきご飯も食べられなくなって最期は燃え尽きたように亡くなってしまいます。
また、猫の甲状腺機能亢進症は不整脈を併発することもあり、その場合突然死するケースもあります。
甲状腺機能亢進症の早期発見、早期治療について
甲状腺機能亢進症は、発見が遅れると臓器へのダメージがどんどん大きくなっていきます。
猫が甲状腺機能亢進症になった場合の平均寿命は1年半~2年とされていますが、慢性腎不全を併発している場合はもっと短くなり、平均寿命は約6ヵ月です。
しかし、早期に発見し適切な治療を受けられれば、長期的な予後が期待できます。
甲状腺機能亢進症でみられる症状
猫の甲状腺機能亢進症の症状は下記の通りです。
・攻撃的になる
・落ち着きがなくなる
・年齢の割に活発
・目がギラギラしている
・鳴き声が大きくなる
・多飲多尿
・下痢
・嘔吐
甲状腺機能亢進症になりやすい猫
甲状腺機能亢進症になりやすい猫種は特にありません。
雄・雌、去勢・未去勢に関わらず、すべてのシニア猫がかかる可能性があります。
甲状腺機能亢進症を発症したほとんどの猫が10歳以上の老猫で、8歳以下の若い猫が発症する可能性は低いです。
甲状腺機能亢進症と併発しやすい疾患
甲状腺機能亢進症は、慢性腎不全や肥大型心筋症、高血圧症などの命に関わる病気を併発しやすいです。
特に慢性腎不全には、併発したことに気づけない場合があるため要注意です。
通常、慢性腎不全になると血流量が少なくなりますが、甲状腺機能亢進症によって血流量が増えることで、血液検査をしても慢性腎不全に気づけない場合があります。
肥大型心筋症は、心臓の筋肉が分厚くなり、血液の通る心臓の内腔を押しつぶしてしまうことで突然死することもある怖い病気です。
肥大型心筋症に罹患した猫が甲状腺機能亢進症を併発すると、心肥大がより重度となる可能性があります。
猫の甲状腺機能亢進症の原因
甲状腺機能亢進症は、猫の甲状腺が腫瘍化、過形成することで、甲状腺ホルモンの分泌が異常に活発になる病気です。
猫の甲状腺が腫瘍化、過形成する原因については現段階で解明されていませんが、代謝や環境、遺伝などが相互に作用していると考えられます。
そのため猫の甲状腺機能亢進症を予防することは困難です。
甲状腺の働きとは?
甲状腺は、喉の気管にある蝶のような形をした臓器です。
甲状腺は、体の代謝をサポートする甲状腺ホルモンを分泌し、新陳代謝を促進する働きがあります。
甲状腺ホルモンの分泌が減ったり増えたりすると様々な症状があらわれます。
甲状腺ホルモンの分泌量が減る「甲状腺機能低下症」の場合は、元気がなくなったり疲れやすくなったりするのが特徴です。
反対に、甲状腺ホルモンの分泌量が増える「甲状腺機能亢進症」の場合は、食欲が増す、攻撃的になるなどの症状がみられます。
甲状腺クリーゼに要注意
甲状腺機能亢進症に罹患している猫が強いストレスを感じたり興奮したりすると、甲状腺クリーゼに陥る可能性があります。
甲状腺クリーゼは、甲状腺ホルモンが多くなりすぎると起こる急性甲状腺中毒の一種です。
甲状腺クリーゼになると頻呼吸や発熱、失明、神経異様などが見られる場合があり、最悪の場合死亡してしまうケースもあります。
ストレスや興奮以外にも、抗甲状腺薬突の中止や甲状腺の手術が理由で甲状腺クリーゼに陥る可能性もあるため要注意です。
甲状腺クリーゼは放置していても自然に治ることはなく、最悪の場合余命を縮めてしまいかねないため、疑わしい症状があれば早めに動物病院へ連れていきましょう。
猫の甲状腺機能亢進症の検査法
猫に甲状腺機能亢進症を疑う症状があられた場合、すぐに動物病院へ連れていきましょう。
血液検査によって甲状腺ホルモンの数値を調べれば、甲状腺機能亢進症かどうかがわかります。
血液検査で血液中のT4濃度を測定し、高値(>5.0μg/dl)だった場合は甲状腺機能亢進症です。
しかし、慢性腎不全に罹患している場合はT4の数値が高くならない場合もあり、甲状腺機能亢進症の発見が遅れる可能性もあります。
猫に甲状腺機能亢進症の症状が見られるのに、慢性腎不全やそのほかの疾患によってT4の数値が高くない場合は、合併症を引き起こしていることを考えさまざまな検査をすすめられることもあります。
猫の甲状腺機能亢進症の治療
猫が甲状腺機能亢進症になった場合は、病状によって外科的治療や内科的治療、その他の治療が行われます。
内科的療法
内科的治療では、甲状腺ホルモンが合成するのを抑える抗甲状腺薬の投薬を行います。
抗甲状腺薬は生涯に渡って飲み続ける必要があり、猫によっては副作用が出ることもあるため、定期的に動物病院で体調チェックや甲状腺ホルモンの数値を測定をしながら投薬していくのが大切です。
人体薬であるメルカゾールを使用するケースもありますが、現在は猫専用であるチロブロック錠(チアマゾール)が発売されています。
抗甲状腺薬の投薬量は、猫の症状や甲状腺ホルモの量によって変わるので、定期的に通院して検査する必要があります。
抗甲状腺薬の処方や診察にかかる医療費は、1回で10,000~20,000円程度です。
外科的療法
内科的治療で効果が見られない場合や甲状腺に悪性腫瘍がある場合は、手術で甲状腺を摘出する外科的治療が検討されます。
根本治療なので日々の投薬が必要なくなり、生活の質向上が期待できるのがポイントです。
しかし、猫の年齢や甲状腺機能亢進症の進行具合によっては摘出手術ができない、もしくは手術後も甲状腺ホルモンの補充療法が必要になる場合もあります。
両方の甲状腺を摘出する場合は、甲状腺ホルモンを分泌できなくなってしまうため、手術後は生涯に渡って甲状腺ホルモン薬を投与していかなくてはなりません。
手術は麻酔やさまざまな合併症のリスクを伴うため、かかりつけ医としっかり相談するようにしましょう。
甲状腺摘出手術やそれに伴う入院をした場合の治療費は、15~30万円程度で、甲状腺を1つ摘出するのか、両方とも摘出するのかによっても差があります。
その他の治療法
近年では、甲状腺ホルモンの材料となるヨードを制限した療法食も販売されているため、食事療法で甲状腺機能亢進症をコントロールする選択肢もあります。
しかし、食事療法ではそのほかのキャットフードを一切口にしてはいけないため、好き嫌いの多い猫や普段からおやつを食べている猫などは甲状腺機能亢進症用フードに飽きてしまうかもしれません。
ヨードを制限したフードはヒルズ社から「y/d」という商品が出ています。
「y/d」の値段は2kgで6,000~7,000円です。
そのほかにも、放射性ヨウ素治療がありますが現在日本では実施不可能となっています。
猫の甲状腺機能亢進症におすすめの保険は?
ここでは猫の甲状腺機能亢進症、および猫に合ったおすすめのペット保険、比較・選び方について解説します。
全てのペット保険で補償の対象外である去勢の費用等の項目は除き、あくまで保険会社・プランで差別化になるポイントに絞って解説します。
他サイトのようなランキング形式ではなく、あくまで猫目線で解説していきます。
猫のペット保険加入の選び方のポイント
・歯科治療(歯周病等)②加入後に発症した先天性、遺伝性疾患が補償されるか
③通院・手術・入院を補償するフルカバー型のペット保険の中でも通院は他社と比較しても手厚いか
④更新の際に「来年度からの傷病や部位補償の対象外」とする可能性がないか
①猫のなりやすい病気が補償されるか確認
ペット保険は保険会社によって補償する病気や、補償の対象外となる項目が異なります。
中には猫がなりやすい、歯周病を含む一切の歯科治療を補償の対象外としているペット保険も存在します。例えば「プリズムコール」では一切の歯科治療が補償の対象外です。
また、「日本ペット少額短期保険:いぬとねこの保険」では「歯肉に触れる治療は補償されるが、歯に触れる治療は補償の対象外」といった細かい制限があります。
特に歯科治療は保険会社によって補償されるかが異なりますので、必ず保険約款や重要事項説明書を確認することをおすすめします。
また公式HPでも「保険金のお支払いできない事例」の中に記載されていることがほとんどですので必ず確認しましょう。
補足になりますが、予防目的の歯石除去等は全てのペット保険で補償の対象外なので注意しましょう。
猫がなりやすい病気で補償の対象外か確認すべき病気
②加入後に発症した先天性、遺伝性疾患が補償されるか
全てのペット保険で加入前に発症している先天性、遺伝性疾患は基本的には補償の対象外となってしまいますが、加入後に発症した先天性、遺伝性疾患を補償するかどうかは保険会社によって異なります。
猫の甲状腺機能亢進症は遺伝的な要素も絡むことがある疾患です。
こちらも併せて公式HP内の「保険金をお支払いできない事例」や保険約款・重要事項説明書を確認し、加入後に発症した先天性疾患が補償されるかしっかり確認しましょう。
③通院・手術・入院を補償するフルカバー型のペット保険の中でも通院補償の手厚さを重視するのがおすすめ
猫がなりやすい病気である「甲状腺機能亢進症」や「腎臓病」は長期もしくは複数回の治療が必要になる疾患です。また「尿結石」は症状が重い場合、外科手術を伴う高額治療が必要になる傷病です。
そのため、猫には「通院・手術・入院を補償するフルカバー型のペット保険」に加入することがおすすめです。
しかし、猫は甲状腺機能亢進症等の慢性疾患になりやすいのに対し、そこまで手術の可能性は高くありません。そのため猫にはフルカバー型の中でも通院補償が他社より手厚いペット保険に加入することをおすすめします。
④更新の際に「来年度からの傷病や部位補償の対象外」とする可能性がないか
ほとんどのペット保険が一年契約となっており、契約を毎年更新していくことで終身の補償となっています。
つまり、ペット保険に加入すると毎年契約更新の審査があります。
中には「前年度にかかった傷病や慢性疾患」等の、特に治る見込みが少ない、再発の可能性が高い慢性疾患を、更新の際に「来年度から補償の対象外とします。」と条件を付け加えてくる保険会社があります。
もちろん中には「更新の際に条件を付け加えることはありません」といった記載をしているペット保険もあります。
猫の甲状腺機能亢進症は慢性疾患のため、かかってしまったら一生の付き合いが必要な病気です。
加入を検討しているペット保険会社の「更新時の対応」についても必ず確認することをおすすめします。
また、ペット保険比較アドバイザーではそういった情報も一つの記事内でまとめていますのでぜひ一度ご確認ください。
猫におすすめのペット保険をご紹介!
最後に、今回ペット保険比較アドバイザーでは猫におすすめのペット保険をご紹介します。
おすすめの理由としては上記で説明した甲状腺機能亢進症含めた猫のペット保険の選び方、ポイントや条件をすべて満たしているからです。
また、アニコムに関しては「腸内フローラ測定」を年一で行えるため、猫の死因ランキング1位である腎不全の予防までできる他、外出しずらい猫には有効な健康チェックです。
測定結果によっては血液検査も無料で受けることができます。
ただし、細かい補償内容や金額についてはもちろん違いがありますので必ず重要事項説明書や保険約款、パンフレットや公式HPを確認してください。
あくまで参考ですが、そもそも病気にさせたくないと考える飼い主様にはアニコムがおすすめです。
| メリット | デメリット | |
| ・歯科治療も補償 ・「腸内フローラ測定」等の予防型サービスも付帯 ・手術は一回当たり最大14万円まで保障(補償割合70%プラン) |
保険料が高い
※健康割増引制度により保険の利用状況によって割増引の適応【可】 |
 2年目以降のご契約継続について
2年目以降のご契約継続について弊社の商品の保険期間は1年間ですが、ご契約には「継続契約特約」を適用して引受をさせていただいておりますので、解約等のお申し出がない限り満期後は、原則ご契約は自動的に継続となり、終身ご継続いただけます。
※ご注意
・ご契約者または弊社より別段の意思表示があった場合には、ご契約は継続となりません。
・自動的にご契約が継続とならない場合や、商品改定により保険料、補償内容などが変更となる場合があります。
引用:重要事項説明書
補足:先天性疾患が発症する前に!遅くとも7.8歳までには加入しよう
ペット保険は、加入する前に発症している先天性疾患は補償の対象外となります。
そのため、病気になってから保険に加入しようとしても、肝心のその病気の治療費は補償の対象外になってしまいます。
また、加入後に発見できた病気であっても先天性疾患を補償の対象外としているペット保険や、慢性疾患にかかると更新できない保険もあります。
また一般的にペット保険では8~12歳で新規加入年齢を設定していることがほとんどです。早いところでは7歳で新規加入を締め切るペット保険もあります。
「健康なうちに加入しないと意味がない」「また年齢制限に引っかからないから保険の選択肢が広がる」という意味で遅くとも7~8歳までにはペット保険の加入、少なくとも検討をすることをおすすめします。
補足ですが、アニコムやプリズムコールではシニア向けのペット保険商品もあります。しかし保険料も高くなり、補償内容のグレードも普通のプランより下がってしまいます。
高齢・シニア向けのペット保険については下記の記事でも解説していますのでぜひ参考にしてください。
よくある質問
愛猫の喉のあたりが腫れているような気がします。甲状腺機能亢進症でしょうか。
飼っている猫が甲状腺機能亢進症と診断されました。長生きできるでしょうか?
ペット保険は必要?

ペットには公的な保険制度がありません。そのため治療費の自己負担額は100%です。
もしもの時に、お金を気にせずペットの治療に専念できるよう健康なうちにペット保険に加入することをおすすめします。
また、病気になった後では加入を断られる可能性があります。
ペット保険比較表や記事を活用するのがおすすめ!
ペット保険比較アドバイザーでは、ペットに合った保険の選び方やペットの健康に関するお役立ち記事を公開しております。
記事と合わせて比較表も活用することで、ペットと飼い主様に合った保険を選ぶことができます。
また、保険会社のデメリット等も理解できるので、後悔しないペット保険選びができます。
ペット保険への加入を検討されている方はぜひご活用ください。
【猫の甲状腺機能亢進症】まとめ
今回、ペット保険比較アドバイザーでは
・猫の甲状腺機能亢進症の原因
・猫の甲状腺機能亢進症の治療法
・猫が甲状腺機能亢進症になった場合の余命